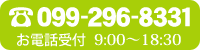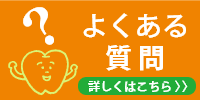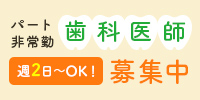口内炎ができる原因 ~主な5つの原因と対処法~
2025.04.13
カテゴリー: 院長日記
今回は口内炎ができる原因について解説していきます。
Table of Contents
Toggle2.口内炎ができる原因
口内炎は一度できるだけでも厄介ですが、繰り返し発生する場合、何らかの原因が体内や生活習慣に潜んでいることがあります。ここでは、口内炎を引き起こす主な原因を5つに分けて解説します。
2-1. 栄養不足による影響
健康な口腔内環境を維持するためには、体に必要な栄養素を十分に摂取することが重要です。特に次のような栄養素が不足すると、口内炎ができやすくなります。
- ビタミンB群の不足
ビタミンB群(特にB2やB6)は、粘膜の健康を保つために欠かせない栄養素です。不足すると、口腔内の粘膜が弱くなり、炎症や傷が治りにくくなるため、口内炎が発生しやすくなります。食事が偏っている方やダイエットをしている方に見られることがあります。 - 鉄分や亜鉛の欠乏
鉄分が不足すると貧血を引き起こし、体全体の免疫力が低下します。また、亜鉛は細胞の修復や再生に関与していると言われ、不足すると傷が治りにくくなるため、口内炎が慢性化する原因となります。鉄分や亜鉛が多く含まれるレバー、貝類、ナッツ類などを積極的に摂取することも有効です。
2-2. ストレスと免疫力低下
現代社会で避けられないストレスも、口内炎の大きな原因となります。ストレスが体に与える影響は、目に見えない形で広範囲に及びます。
- ストレスが体に与える影響
ストレスが長期間続くと、ホルモンバランスが崩れ、免疫力が低下します。その結果、体が細菌やウイルスに対抗しにくくなり、口内炎を発症しやすくなります。 - 睡眠不足と口腔内環境の関連性
睡眠不足もストレスと同様に免疫力を低下させる要因です。特に睡眠中は体が修復や回復を行う時間であるため、十分な睡眠が取れないと粘膜の再生が遅れ、口内炎の治りが悪くなることがあります。
2-3. 口腔内のトラブル
口腔内の物理的な刺激も口内炎の原因となります。毎日のケアや口腔内装置を見直すことで予防できる場合があります。
- 歯の矯正装置や義歯による物理的刺激
矯正装置や義歯が合わない場合、口の中に繰り返し擦れる部分ができてしまい、そこが傷ついて口内炎になることがあります。装置が原因と思われる場合は、歯科医に相談して調整を行いましょう。 - 歯磨きや舌ブラシの使いすぎ
強く磨きすぎることで、歯や歯茎だけでなく、粘膜にもダメージを与える可能性があります。特に舌ブラシの過剰な使用は舌を傷つけやすいので注意が必要です。
2-4. 全身疾患や薬剤の影響
口内炎は、体の他の疾患や薬剤の副作用によっても引き起こされることがあります。
- 胃腸の不調や消化器系疾患
胃腸の調子が悪いと、口腔内の健康にも影響が及びます。例えば、胃の不調によるビタミンやミネラルの吸収不足が、間接的に口内炎を引き起こすことがあります。 - 特定の薬剤(抗がん剤や免疫抑制剤)の副作用
抗がん剤や免疫抑制剤の使用による副作用として、口内炎が生じることがあります。これらの薬剤は免疫力を低下させ、口腔内の環境を変化させるため、炎症が起こりやすくなります。薬剤が原因の場合は、医師に相談して適切なケア方法のアドバイスをもらいましょう。
2-5. ウイルスや細菌感染
口内炎の原因には、ウイルスや細菌感染も含まれます。例えば、ヘルペスウイルスによる感染は「ヘルペス性口内炎」を引き起こします。このタイプの口内炎は発熱や倦怠感を伴うことが多く、通常の口内炎とは異なる症状が見られます。こうした感染が疑われる場合は、早めに医師の診断を受けることが必要です。
まとめ
口内炎が繰り返しできる原因は、栄養不足やストレス、口腔内の物理的刺激、全身疾患、さらにはウイルス感染までさまざまです。それぞれの原因に対処することで、口内炎の頻度を減らし、快適な生活を取り戻すことができます。次の記事では、これらの原因を踏まえた予防策について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!